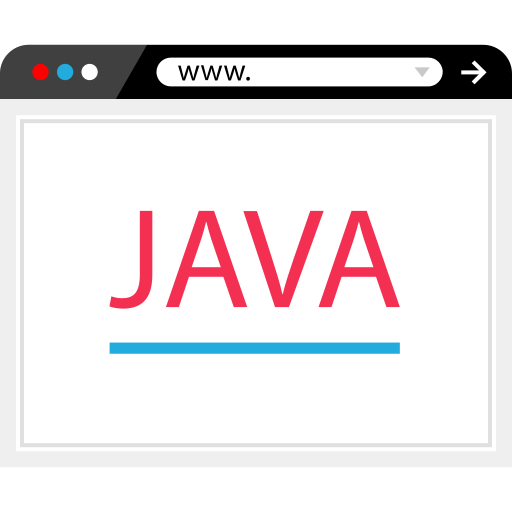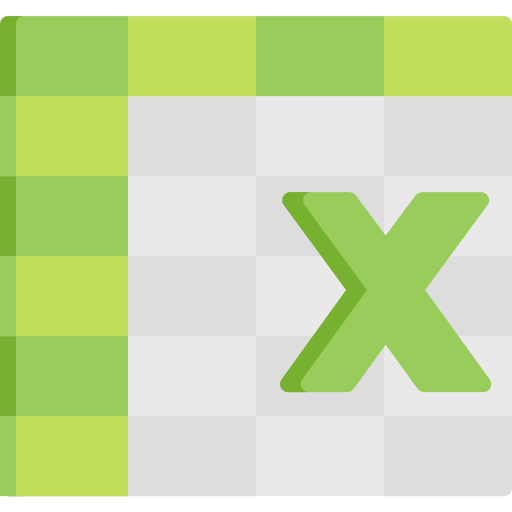主な内容の要点
JavaScriptでは、throw文を使うことで自分でエラー(例外)を発生させることができます。これにより「ここで処理を止めたい」「特定の条件でエラーを知らせたい」といった場面を自由に作れます。
基本ポイント
throw文の役割- プログラムの途中で「例外」を発生させる命令。
- 例外が発生すると、その場で処理が中断され、
catchブロックに処理が移る。
- 書き方
throw 値;- 値には通常
Errorオブジェクトを使うが、文字列や数値なども指定可能。
- 値には通常
try...catchとの組み合わせthrowで発生させた例外は、try...catchで受け止める。catchブロックの引数に、throwで渡した値が入る。
サンプルコード(初心者向け解説付き)
function checkResult(point) {
try {
if (point < 50) {
throw '不合格です'; // 条件に合わないときに例外を発生
}
console.log('得点 ' + point);
console.log('合格です');
} catch(e) {
console.error(e); // throwで渡した値を表示
}
}
console.log('Start');
checkResult(82); // → 合格
checkResult(40); // → 不合格
console.log('End');
pointが50未満なら「不合格です」という例外を投げる。catch(e)でその例外を受け取り、console.errorで表示。- これにより「条件に合わないときに処理を止めて、エラーを伝える」ことができる。
初心者へのヒント
throwは「自分でエラーを作る」ための道具。try...catchは「エラーを受け止める」ための道具。- 実際の開発では、
throw new Error("メッセージ")のようにErrorオブジェクトを使うのが一般的。
👉 まとめると、「条件に合わないときにthrowで例外を発生 → catchで受け止めて処理を続ける」という流れを理解すれば、初心者でもエラー処理の基礎をつかめます。
この仕組みを覚えると、プログラムが「ただ止まる」のではなく、「エラーを伝えて安全に続ける」ことができるようになります。