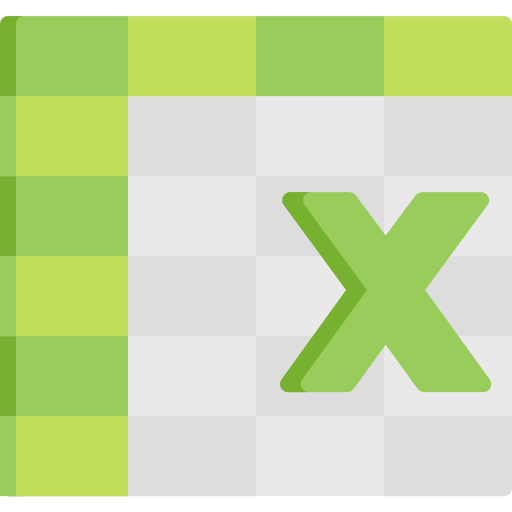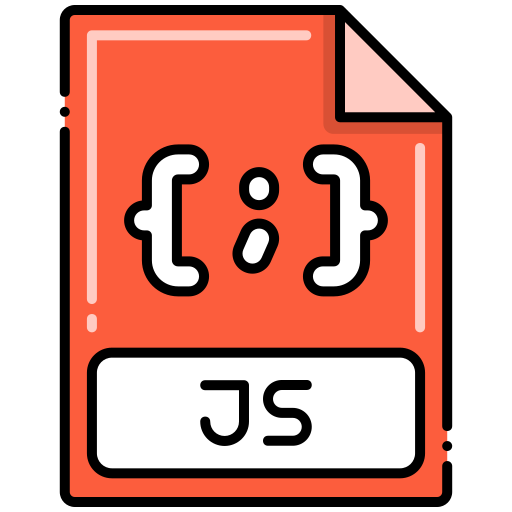「開発環境判定」とは何を判定するのか
まず言葉を整理します。
ここでいう「開発環境判定」は、ざっくり言うと
「今このコードは“本番”で動いているのか、“開発用”で動いているのか」
を判定するためのユーティリティです。
業務システムでは、同じコードでも
開発環境(ローカル、開発サーバー)
ステージング環境(テスト用サーバー)
本番環境(お客様が使う環境)
のように、複数の環境で動きます。
そして、環境によってやりたいことが変わる場面がたくさんあります。
ログを詳しく出すのは開発環境だけにしたい。
ダミー API を使うのは開発環境だけ、本番では本物の API を使いたい。
危険なデバッグ用ボタンは本番では絶対に表示したくない。
こういう「環境ごとの振る舞いの違い」を、
コードの中で安全に表現するために「開発環境判定」ユーティリティを用意します。
いちばん基本の考え方:環境名をどこかに持っておく
開発環境判定の本質はとてもシンプルです。
「今は development なのか、production なのか、test なのか」
という“環境名”をどこかに持っておき、
それを見て分岐する、というだけです。
フロントエンドでもバックエンドでも、よくあるのは
NODE_ENV という環境変数を使う
ビルド時に process.env.XXX を埋め込む
設定ファイル(config)に env: "development" のように書く
といったパターンです。
JavaScript のユーティリティとしては、
「環境名を見て、分かりやすいフラグを返す関数」を用意しておくのが定番です。
Node.js やビルド環境での基本形
process.env.NODE_ENV を使った判定
Node.js や、Webpack / Vite / Next.js などのビルド環境では、process.env.NODE_ENV がよく使われます。
まずは、これをラップしたユーティリティを作ってみます。
function getEnv() {
const env = process.env.NODE_ENV || "development";
return {
name: env,
isDev: env === "development",
isProd: env === "production",
isTest: env === "test",
};
}
使い方はこうです。
const env = getEnv();
if (env.isDev) {
console.log("開発環境用のログを出す");
}
if (env.isProd) {
console.log("本番環境なので、余計なログは出さない");
}
ここでの重要ポイントは二つです。
環境名を文字列のままバラバラに扱わないこと。"development" や "production" を直接 if に書かず、isDev や isProd にまとめること。
これをやっておくと、
「環境名の表記を変えたい」「環境を増やしたい」となったときも、getEnv の中身だけ直せば済みます。
フロントエンドでの開発環境判定(ビルドツール前提)
import.meta.env や process.env を使う場合
Vite や一部のツールでは import.meta.env.MODE、
Webpack 系では process.env.NODE_ENV がフロント側にも埋め込まれます。
例えば Vite なら、こんなユーティリティが書けます。
function getEnv() {
const env = import.meta.env.MODE || "development";
return {
name: env,
isDev: env === "development",
isProd: env === "production",
};
}
React + Webpack などなら、さきほどの process.env.NODE_ENV 版をそのままフロントでも使えます。
大事なのは、
「どのビルドツールを使っていても、“環境名を一箇所でラップする”」
という発想です。
環境ごとに挙動を変える具体例
例1: ログ出力を開発環境だけにする
本番環境で console.log を大量に出すのは、
パフォーマンスやセキュリティの観点からあまり良くありません。
そこで、ログ用のユーティリティを環境判定付きで用意します。
const env = getEnv();
function debugLog(...args) {
if (!env.isDev) return;
console.log("[DEBUG]", ...args);
}
使う側は、ただ debugLog を呼ぶだけです。
debugLog("ユーザー情報", user);
開発環境ではログが出る。
本番環境では何も出ない。
という挙動になります。
ここでの深掘りポイントは、
「呼び出し側は環境を意識しない」ようにしていることです。
環境判定はユーティリティの中に閉じ込める、という設計がとても大事です。
例2: API のベース URL を環境ごとに変える
開発環境では https://dev-api.example.com、
本番では https://api.example.com を叩きたい、というケースはよくあります。
const env = getEnv();
function getApiBaseUrl() {
if (env.isProd) {
return "https://api.example.com";
}
return "https://dev-api.example.com";
}
使う側はこうです。
async function fetchUser() {
const baseUrl = getApiBaseUrl();
const res = await fetch(`${baseUrl}/user`);
return res.json();
}
これで、ビルド時に NODE_ENV だけ変えれば、
同じコードで開発環境・本番環境を切り替えられます。
「環境名を文字列でベタ書きしない」ことの重要性
初心者がやりがちなパターンは、
アプリのあちこちにこう書いてしまうことです。
if (process.env.NODE_ENV === "development") {
// 何か
}
これをいろんなファイルに散らばせると、
後から環境名を変えたくなったときに地獄を見ます。
例えば、「development ではなく dev にしたい」となったら、
全ファイルを探して置換しないといけません。
それを避けるために、
環境名は一箇所で受け取る。
そこから isDev や isProd のようなフラグを生やす。
アプリ本体は、そのフラグだけを見る。
という構造にしておくことが、業務コードとしてはとても重要です。
「開発環境判定」を使うときの注意点
一つだけ意識しておいてほしいのは、
「環境判定に頼りすぎない」ということです。
何でもかんでも
開発環境なら A
本番環境なら B
と分岐し始めると、
環境ごとに挙動がバラバラになり、テストも難しくなります。
開発環境判定を使うのは、主に次のようなところに絞るのが健全です。
ログやデバッグ用の機能。
モック API と本物 API の切り替え。
危険な操作(データ削除など)のガード。
ビジネスロジックそのものは、
できるだけ環境に依存しないように書く、という意識を持っておくと、
長期的にメンテしやすいコードになります。
小さな練習で感覚をつかむ
簡単な Node.js スクリプトを作って、NODE_ENV を変えながら動きを確認してみてください。
例えば、次のようなコードです。
function getEnv() {
const env = process.env.NODE_ENV || "development";
return {
name: env,
isDev: env === "development",
isProd: env === "production",
};
}
const env = getEnv();
console.log("env.name:", env.name);
console.log("isDev:", env.isDev);
console.log("isProd:", env.isProd);
これを
NODE_ENV=development node app.js
NODE_ENV=production node app.js
NODE_ENV=test node app.js
のように実行してみると、
「環境変数 → ユーティリティ → フラグ」という流れが体感できます。
その感覚をそのままフロントエンドにも持ち込んで、
自分のプロジェクト用の
getEnvisDevisProd
を一つ決めておく。
それができた瞬間、あなたのコードは
「場当たり的な環境分岐」から
「設計された環境判定ユーティリティ」に一段レベルアップします。